こんにちは、剣道未経験のかあさんです😊 今回は、保護者が防具をつけて参加する「親子試合体験」で、剣道の試合ルールや所作にふれて驚いたこと、そして子どもたちの成長を実感したエピソードをご紹介します。
初めての防具体験!想像以上にハード…
親子で剣道対決をするイベントがあり、私も防具をつけて参加することに。面・胴・垂れを装着してまず感じたのは…
「重い!暑い!視界が狭い!」
この状態で毎回稽古をしている子どもたちを、本当に尊敬しました。
親子対決スタート!たった2分がこんなに長いなんて…
ちなみに剣道の試合時間は年齢によって異なります。
- 小学校低学年:2分
- 小学校高学年~中学生:3分
- 高校生・大学生:4分
- 一般:5分
※大会によってルールが異なる場合もあります。勝敗がつかない場合は延長戦(一本勝負)や判定で決まることも。
実際に試合をしてみて、「たった2分なのに、息が切れるほどきつい!」ということに驚きました。
📌 試合中のリアルすぎる私の体験…!
- 面しか狙えない(余裕ゼロ)
- 息が上がって苦しい
- 子どもに体当たりされてヨロヨロ…
- 竹刀を叩かれて手がしびれる…
👩🦰「母、完敗。」結果は2本負けでした。 でもそれ以上に、子どもたちの集中力と体力に脱帽です。
意外と知らない!? 剣道の反則ルール
試合中には以下のような反則もあります:
- 竹刀を落とす → 反則(竹刀は“命”とされます)
- 場外や消極的な姿勢も反則対象
- 反則2回で1本負け
知らないと、うっかりやってしまいそうなルールばかり!
試合の始まり方:所作の流れ
剣道では、試合前後の所作がとても大切にされています。
1️⃣ 試合場への立礼(りつれい) → 正面に向かって一礼。「この場に入らせていただきます」という気持ちを表します。
2️⃣ 提げ刀(さげとう)の姿勢で入場 → 左手で竹刀を持ちまっすぐ下げ、背筋を伸ばして立礼位置へ。試合線から3歩の距離を目安に立ちます。
3️⃣ 相互の礼(目礼) → 相手の目を見たまま、軽く15度ほど頭を下げて礼を交わします。
4️⃣ 帯刀(たいとう) → 竹刀を左手で持ち、左腰に当てる所作です。
5️⃣ 試合線へ移動 → 帯刀のまま、右足から3歩で開始線に立ち、竹刀を抜きます。
6️⃣ 蹲踞(そんきょ) → つま先立ちのまましゃがみ、かかとにお尻をつける姿勢。竹刀を前に構えたまま集中します。
7️⃣ 主審の「始め!」を待つ → 気持ちを整え、合図で試合開始!
試合終了の流れ(所作のポイント)
1️⃣ 「止め!」の合図で試合終了 → 主審の号令で攻防をやめ、開始線に戻ります。
2️⃣ 中段の構えで待機 → 竹刀を構えて立ち、主審の勝敗宣告を待ちます。
3️⃣ 「勝負あり」の宣告 → 結果が出ても感情を表さず、礼を忘れないことが大切。
4️⃣ 蹲踞・おさめ刀 → 蹲踞して竹刀を納めます。
5️⃣ 立ち上がり、帯刀して左足から5歩下がる
6️⃣ 相互の立礼(さげとうで目礼) → 勝敗にかかわらず、相手への感謝と敬意を込めて15度の礼。
7️⃣ 試合場から退場 → 立礼の位置まで下がり、提げ刀の姿勢で退場します。
団体戦の場合
- 試合後、両チームが整列して立礼。
- 主審の合図で礼を交わし、静かに退場します。
❌NGマナー:ガッツポーズは禁止!
剣道では、
- ガッツポーズ
- 声を上げて喜ぶ
- 悔しがる動作
などはすべてマナー違反とされます。 → 「相手への敬意」と「礼節」が最優先の武道文化です。
剣道の応援スタイルにもびっくり!
- 応援は「拍手のみ」
- 声援・メガホン・楽器は禁止
🔇 なぜ?
- 審判や選手への妨げになる可能性があるため
- 静寂を重んじ、音も判定材料になるから
実際に観戦してみると、静かな中での気合や音がとても印象的でした。
まとめ|体験してわかった剣道の奥深さ
今回の親子剣道体験を通じて、「剣道の試合ルール」や「所作」「礼儀の大切さ」を実感できました。
保護者との試合に勝って喜ぶ子、負けて悔し泣きしてしまう子、普段の稽古では見られない様々な表情を見ることができて、心温まる日となりました。
剣道には「打って反省、打たれて感謝」という言葉があります。武道における礼儀や謙虚さを表しており、相手を尊敬し、自己の成長に努めることを促します。
「礼に始まり、礼に終わる」――その精神の深さにふれた、貴重な一日でした。
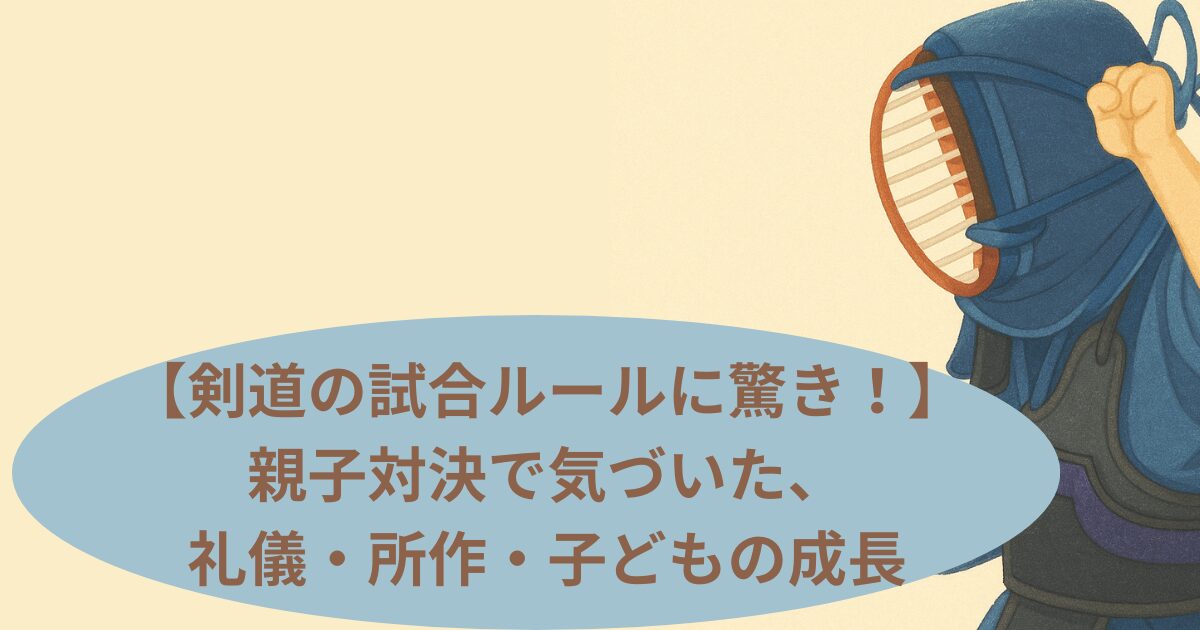


コメント